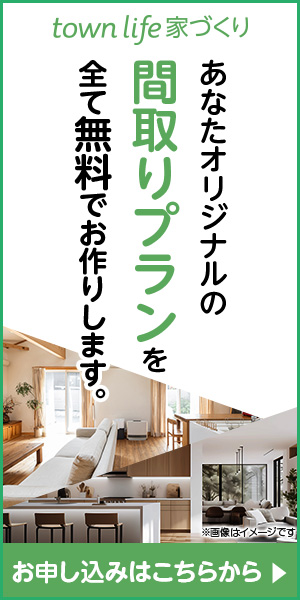パート6です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09
マンション管理士の活用。。。パート6
|
452:
マンション管理研究会
[2011-11-29 20:52:40]
求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため
|
|
453:
コ"ルコ"13
[2011-11-29 20:53:05]
おお、弁護士に確認して頂けるとは!ありがとうございます。
前に、委任状票を分割できるかという論点で、しょうもないレスをしたので、色々考えてみました。 |
|
454:
管理侍
[2011-11-29 21:05:24]
|
|
455:
コ"ルコ"13
[2011-11-29 21:47:17]
>何の意思もない委任なら、受任者が総会での議事、質疑応答を聞いた上で判断して議決権を行使すればよい
そうなんですよ。何はともあれ、判断すべき。その点、監事が按分で投票って何?判断放棄かい?そんなことも考えています。 特に、一般的な理事長宛てを選択せず、監事を委任先に選択した組合員は、その事実だけで職責への特別な期待があると考えています。そんなことから、肢4も悩ましい。 |
|
456:
管理侍
[2011-11-29 22:51:50]
ゴルゴさん
肢4は「総会出席者の賛否の比率に応じて」を無視して考えては? そうすると「委任状を分けて使えるか」という問題になります。 「比率に応じて」というのはあくまで分け方の話ですからね。 |
|
457:
マンション管理研究会
[2011-11-29 23:47:16]
マンション管理センターの考えかたが正しいかどうかは別にして、私は合格するために毛色の違う4にしました。
|
|
458:
匿名さん
[2011-11-30 00:40:41]
問題は50→1の順で解くといいよ。適正化法の46-50は何が何でも5問とらないといけません。
7分で解いて3分のアドバンテージをとる。 |
|
459:
コ"ルコ"13
[2011-11-30 01:02:10]
管理侍さん、マンション管理研究会さん
受験という場を大前提にすると、全く別のアプローチも考えることもできると思います。 個数問題を除く設問は、 ①「正しいものはどれか」「誤っているものはどれか」 ②「適切なものはどれか」「適切でないものはどれか」 に区分されます。 ①のパターンは、○○○×(又は×○○○)の1つのモノを探す設問であるのに対し、 ②のパターンは、◎、○、△、×、××の中から、◎又は××を探す設問と割り切る。そんなアプローチが考えられます。 問29は、②の「適切でないものはどれか」になります。 そうすると、 肢1,2,4は「…できる。=can」に対し、肢3は「…なければならない=must」と明らかにニュアンスが違います。 肢3の「…なければならない=must」は、例外なしに該当するニュアンスを込めている表現と考えます。 肢3は、例外ケースが考えられると考えますので、『××』かなと。 肢4は、個人的にはイマイチ度満点ですが、「…できる=can」と可能性に言及している範疇にとどまっていることから、 『×』止まりかなと考えました。 そこで、個人的に適切でない度合いは、肢3××>肢4×と考えています。 そうは言っても、マンション管理研究会さんの自説(=監事に期待するアプローチ)に、私も共感しているところがあります。そのため、監事の監事たる役割に期待大して、肢4に『××』と付けたい気持ちを捨てきれないので、確信までには至っておりません。 |
|
460:
マンション管理研究会
[2011-11-30 01:55:51]
ありゃま、ゴルゴもこういうの好きですねー。
問29の論点は たぶん、出題者は「理事会決議に理事長は拘束される、監事は拘束されない。」と考えてるんです。 以前、マンション管理センターに電話で質問したとき、「理事会決議に理事は拘束されるが組合員は拘束されない」とかいってたんで、内部でそういう見解が浸透してるのかも。 その前提なら1、2,3は適切。 残るは4.不適切なのは4です。 4が適切だとすると2戸もってる区分所有者が委任状を出したとき幹事が2個の議決権の使い分けをすることになり、特別決議の組合員の頭数の過半数という要件の計算ができません。 今年度問題再掲 http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf |
|
461:
コ"ルコ"13
[2011-11-30 08:05:38]
>問29の論点は
>たぶん、出題者は「理事会決議に理事長は拘束される、監事は拘束されない。」と考えてるんです。 この点は、とても説得力があります。うーむ。 |
|
|
|
462:
管理侍
[2011-11-30 08:25:06]
お二人ともマニアック全開ですね。
そして分析、論点など説得力十分。 肢4については賛成派からの委任と反対派からの委任で 監事が使い分ける可能性が理論上あるのではないでしょうか。 委任による議決権の行使は代理人としての行使なので、組合員の頭数は変わりません。 |
|
463:
マンション管理研究会
[2011-11-30 09:17:58]
>>委任による議決権の行使は代理人としての行使なので、組合員の頭数は変わりません。
そりゃ、わかってるけど、どうやって分けるんだい? 売れ残りの10部屋を持ってるデベは議決権10個、頭数は1。 デベが委任状を出して肢4のとおり按分できるとした場合、 賛成反対に10票を6票:4票で割り振ったとしたら、頭数は0.6人と0.4人? こんなことができるなら、「私は0.3人分賛成で0.7人分反対です!」っていう議決権行使もあるのかい? |
|
464:
マンション管理研究会
[2011-11-30 09:52:28]
会社法の規定では下記の通り。
区分所有法に同様の規定はありませんから、議決権の不統一行使を認めるには規約での定めが必要じゃないかと思います。 標準管理規約に議決権の不統一行使の規定はないので、本年度問29の肢4は「不適切」 会社法 第二編 株式会社 第四章 機関 第一節 株主総会及び種類株主総会 第一款 株主総会 (議決権の不統一行使) 第三百十三条 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。 2 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。 3 株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。 |
|
465:
匿:名さん
[2011-11-30 09:57:32]
問29の正解肢は、「4」だと思います。
|
|
466:
匿名さん
[2011-11-30 10:22:21]
解説があったよ
区分所有者数と議決権数を併用する規約の場合、不統一行使は不合理なものとなる。 4.議決権の不統一行使 また、議決権の不統一行使については専有部分はその単一の意思を形成するのが法の建て前である以上専有部分の単位を細分するような不統一行使はそもそも認められません。 複数の専有部分がある場合には議決権自体は形式的には各々の専有部分毎に行使ができますが、区分所有者数と併用する区分法の原則的議事方法の場合には一名の区分所有者を更に分割できませんのでこの場合も不統一行使はできません。 区分所有者数の要件を外す標準管理規約の場合にはこのような制約がありませんが、一人の意思は一個ですから不統一行使は不合理なものとして否定すべきと思われます。 ただし、信託等実質上複数の意思の存在が肯定できる場合には不統一行使も認められるべきです。 |
|
467:
暇人
[2011-11-30 12:42:45]
面白そうなので参戦してみます。
私の見解は肢3です。 まず肢4について。 (1)「複数の別々の人格である委任者から預かった委任状を賛否に分けて行使する」 (→BCDEから委任を受けた受任者Aが、BCの委任状を賛成票を投じ、DEの委任状を反対票を投じる。) ことと >466の解説で言及されているように (2)「一人の人格として賛否両方に票を投じる」 (→複数の区分所有権を保有している一人の人格であるAが(各戸区分所有権に係る議決権のみならず)頭数についても賛否に分けて票を投じる) とは異なります。 今回の設問は、理事長も監事も、複数の人格である複数の区分所有者から複数の委任を受けているので 上記(1)の場合ですから、>463や>466の議論は該当しないと思います。 また、>464で述べられた会社法上不統一行使が許容されているのは、その対象が「株式」だからといえます。 株式は元々「個々の」株式に権利が付帯しているものですから、X氏が100株を持っている場合に50株ずつ別の権利行使をすることが可能なわけです。 もちろん、それを決するのは「一人の人格」としての「100株を保有しているX氏」です。 しかし、100の株式に付帯する権利が「元々別個」なので、(性質は異なる話ですが)上記(2)よりは(1)に近いと言えます。 そして、Aは委任されている以上、BCDEからの「それぞれ別個の受任」について、「それぞれをどのように行使するか」はAの裁量ですから、上記(1)が可能であると結論づけられると思います。 つまり肢4は「適切」と考えます。 肢3はどうでしょうか。 「理事会決議を経た議案につき理事長が反対できるか」という論点の答えは私には分かりません。 これを否定的に考える論拠としては「理事長として理事会決議に加わった以上、それに反対するのは背理」といったものでしょうか。 (これは肢1にも影響するのでしょうが、肢1は「役員を辞任すれば」という留保付なので、この論点に関わらず「適切」といえます。) しかし、少なくとも「他の区分所有者から受任した」分の判断は、受任者としての裁量によって行使できるのではないでしょうか。これを制限するのは、理事会に参加できない委任者の権利を制限するとも思えます(つまり肢3は「不適切」と考えます)。 また、肢2は>461に書かれている理由により(監事は理事会決議で票を投じられません)「適切」と考えます。 以上から、私は肢3が不適切で、本問の回答であると思います。 違ってたらハズカチー。 |
|
468:
管理侍
[2011-11-30 12:55:26]
>463
例示の内容で頭数を分けることは当然できませんね。 ただ複数名から委任を受けている場合には、委任分の議決権を 委任者の意思によって賛成と反対に分けて行使することはあり得るのでは? 例えば10戸所有の組合員Aと1戸所有の組合員B、二名から委任されている場合、 その代理人 監事C(1戸所有)はAの議決権として賛成10、Bの議決権として反対1、 自分の権利として賛成1、という意思表示ができる。 この時の組合員数は賛成2、反対1とカウントする。 だからと言って「総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使える」 とまで言い切るのは私も違和感があります。 ただ無理やりこじ付けて、消去法で考えていくと肢3が残る気がするんですよね。 ゴルゴさんの言う「×」と「××」の考え方です。 是非、弁護士先生への確認をお願いします。 |
|
469:
マンション管理研究会
[2011-11-30 12:57:12]
予備校は肢3だと言ってますよ。
http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/m-kanri/pdf/m-kanri.pdf でもね、肢1は役員を辞任しなければ理事長は賛成票を投じるべきだとも読めますよね。 従って肢1と肢3は同じこと。 マンション管理センターの答えを待つしかないね。 |
|
470:
匿.名さん
[2011-11-30 13:02:40]
>>467 暇人さん
たとえば、 区分所有法第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)第6項では、 「前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、 又は記録しなければならない。」 と規定しています。 どのように取り扱うのでしょうか? |
|
471:
暇人
[2011-11-30 13:04:58]
>だからと言って「総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使える」
>とまで言い切るのは私も違和感があります。 私はこの点も受任者の裁量の範囲内だと思います。 要するに「標準管理規約と民法」上は自由である、ということです。 >でもね、肢1は役員を辞任しなければ理事長は賛成票を投じるべきだとも読めますよね。 ここはある種のひっかけかも知れませんが、問題文は問題文のまま読むべきと思います。 そして「深読みで悩んでしまっても肢3との関係で正しく選べるだろう」というのが出題者の意図のように感じます。 |